萌えた時に萌えたものを書いたり叫んだりする妄想処。生存確認はついったにて。
30 .
September
浅トラ4で藤さんと出した宮司村越×お狐羽田のパラレル無配の小説パートです。
ジャイキリキャラで誰に一番夢を見てるかって羽田ですよ。(開き直り)
清いもんですご安心ください。続きからどうぞー。
ジャイキリキャラで誰に一番夢を見てるかって羽田ですよ。(開き直り)
清いもんですご安心ください。続きからどうぞー。
初めて来た日から、何かがうろついているのは解っていた。
解っていたが、まさかそれが己の祀る神使だとは思わなかった。
禊を終え、綿を詰め込んだ寝具を抱えて本殿に足を踏み入れた村越は、そこに在るものを認めて瞠目した。冷えきった板張りの上にぽつりと座する姿は、ほとんどひとと変わらない。突き出た耳と穂のようにたっぷりとした尾がなければ、化生の者とは気付かないほど、それはしっかりと在った。
村越にとっては「いる」と「ある」の間を行き来し、多くの人間――村越と生業を同じくする者すら含めて――にとっては「いない」に限りなく近いものだ。悩み煩った時だけ概念に縋って「ある」ことにされる、肉の器を持たずに生まれた存在。これほどはっきり見えたことはなかったから、最初は仮装した人間かと思ったが、いつものように自分以外はそれを認識していなかった。なるほど、小さくともいっぱしの神社の御使ともなれば、向こうを透かさぬほど確たるかたちをとれるものだ。
納得して、村越はその後ろ姿に声をかけた。
「そんなところで寒くねえか」
ぴぴ、と毛皮に覆われた耳はちいさく動いたが、振り向きはしない。一般の伝承にたがわず、狐は気位の高い物の怪なのか。布団を下ろし、村越はその肩に手を伸ばした。
「おい」
「うわあああああ!」
呼びかけに言葉を足す間もなく叫ばれた。正していた背がぐにゃりとたわみ、脚がほどけて床に崩れる。驚かれたことに驚いた村越は、背を屈めた体勢で固まった。
「…………さ、わった?」
尾をいっぱいに膨らませたまま、狐が口を聞いた。何とも人くさい仕草でぎこちなく、おそるおそると言った様子で村越を見上げている。
「触ったが、いけなかったか」
引っ込めようとした手を、焦ったように掴まれた。
「さわ、れる」
細く節ばった指は、人間と同じように温度を持ち、しかし深まる夜気に冷えきっていた。思わず握り返し、てのひらのぬくみを移してやるようにくるみこむ。川辺で禊いだ身体は、ようよう体温と血の色を取り戻していた。
「あんた、俺のこと見えるんだ」
神社の縁起に反して、狐の話し方と顔立ちは若い青年のそれだった。人とは齢の重ね方が違うのかもしれない。ようやく村越が己の姿を捉えられる人間であることを認め、彼は勢い良く身体ごと向き直った。
「やっぱり、前の宮司は見えなかったのか」
神職に就いていても、ひとでないものが見える人間はわずかだ。そのわずかにあてはまったからと言って、村越がこの道を選んだわけではないが、見えた方が都合のいいこともある。例えば、今のように。
「ああ、久しぶりだ、前のじいさんもその前のじいさんも、俺が見えなかったから」
ゆらゆらと床を擦る尾が、感情の昂ぶりを表情より如実に表している。一言で一世紀を跨いだ狐は、切れ上がったまなじりを薄く染めて膝でいざった。思いがけず距離を詰められ、これから執り行う儀礼の名が頭をもたげて、村越はほんの少し息を詰まらせる。
「……訊きてえんだが」
身を清めたのも寝具を運び込んだのも、全てはこれの為だ。ここで待っていたということは、物の怪もこちらの義務は承知しているのだろう。問題は、自分がどんなかたちでそれを全うすべきかということだ。
「俺みたいな見える人間とは、今夜はその、本当に寝るのか」
その儀礼についた名は、夜伽と言う。
PR
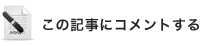
DATE
管理人の他拠点・サーチ様
CONTENTS
COUNTER
PROF.
HN:
シノ
性別:
女性
職業:
底辺社会人
自己紹介:
悪食雑食腐女子。目につくもん大体萌える。(ただしおっさん悪役に限る)
SEARCH:
アクセス解析

